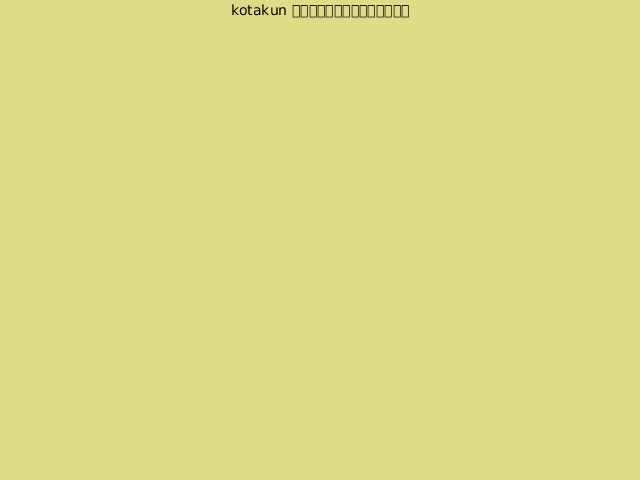Yaleで、遊んで学ぶ日々。
Yaleで、遊んで学ぶ日々。
囲碁、ときどきプログラミング、ところにより経済。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
ODSファイルは、OpenOffice, LIbreOffice Calcの標準形式である。これをRで読み込むには、まず各シートをCSV形式に保存・・・したりする必要はなし!
Omegaプロジェクトから、ROpenOfficeというパッケージが公開されている。今のところ公式レポジトリには入っていないようだが、普通に動くようだ。
Rを開いて。
でインストール。あとはいつもどおり
library("ROpenOffice")
x <- read.ods("file.ods")
でOK。
Omegaプロジェクトから、ROpenOfficeというパッケージが公開されている。今のところ公式レポジトリには入っていないようだが、普通に動くようだ。
Rを開いて。
install.packages("ROpenOffice", repos="http://www.omegahat.org/R")
でインストール。あとはいつもどおり
library("ROpenOffice")
x <- read.ods("file.ods")
でOK。
PR
関数を作る関数。できるのかな、と思ってやってみたらできた。
fun <- function(x) {
out <- function(y) {
cat("x =", x, "\n")
cat("y =", y, "\n")
cat("x+y =", x+y, "\n")
}
return(out)
}
f <- fun(5)
f(2)
# 結果
# 結果
x = 5
y = 2
x+y = 7
データ整理から集計、行列演算、統計分析まで、全部pythonで済ませられないか・・・? データを扱う場合に、それがリストのリストとして定義されているのだと、縦の操作に弱い。例えば、列を対象にした操作ができない。統計ソフトであれば簡単にできる、第1列と第2列を足す、というような単純な操作にforループを回すのではいただけない。Rでいうところのdata.frameにあたるようなオブジェクトはないものかと探したところ、pandasというデータ解析ツールが最近開発されていることを知った。Ubuntu12.04以降は公式レポジトリに入っている。そうでない場合は、公式ページから自分で構築することになる。
pandasは、一言で言えばRのファンがpythonに移植した、という印象で、Rからの漂流者には比較的優しい仕様になっている。一番の売りは、DataFrameというそのものずばりのクラスが定義されていることで、これを科学計算パッケージであるnumpy, scipyと組み合わせることで統計ソフトの仕事を全部こなしてやろう、というプロジェクトと見える。
pandasについては目下のところ勉強中だが、今のところ印象はかなり良い。Rの良い機能を再現しながら、pythonならではの整合性を保っているという印象。計量経済学などはどこまで出来るのかまだわからないが、詰まるところは行列演算と最適化なわけだから、自分で書くこともできるし、そのうち誰かが(あるいはすでに)実装するだろう。実現可能なことはいずれ必ず起こるのだ。
統計ソフトの役割を果たそうとすると、必ずインタラクティブな操作が必要になる。データを読み込んだら、とりあえず集計したり、上の5行くらいを眺めたり、バグがないかチェックしたり、ということをしたい。端末から毎度回すのでは不便すぎるので、必然的にインタープリタを使うことになる。インタープリタ上で、スクリプトファイルを回すには
execfile("filepath.py")
を使う。
では、スクリプトの一部を回すにはどうすればいいか? 専用エディタがあれば普通にある機能だけど・・・。とりあえず、コピペで対処するくらいかな。
pandasは、一言で言えばRのファンがpythonに移植した、という印象で、Rからの漂流者には比較的優しい仕様になっている。一番の売りは、DataFrameというそのものずばりのクラスが定義されていることで、これを科学計算パッケージであるnumpy, scipyと組み合わせることで統計ソフトの仕事を全部こなしてやろう、というプロジェクトと見える。
pandasについては目下のところ勉強中だが、今のところ印象はかなり良い。Rの良い機能を再現しながら、pythonならではの整合性を保っているという印象。計量経済学などはどこまで出来るのかまだわからないが、詰まるところは行列演算と最適化なわけだから、自分で書くこともできるし、そのうち誰かが(あるいはすでに)実装するだろう。実現可能なことはいずれ必ず起こるのだ。
統計ソフトの役割を果たそうとすると、必ずインタラクティブな操作が必要になる。データを読み込んだら、とりあえず集計したり、上の5行くらいを眺めたり、バグがないかチェックしたり、ということをしたい。端末から毎度回すのでは不便すぎるので、必然的にインタープリタを使うことになる。インタープリタ上で、スクリプトファイルを回すには
execfile("filepath.py")
を使う。
では、スクリプトの一部を回すにはどうすればいいか? 専用エディタがあれば普通にある機能だけど・・・。とりあえず、コピペで対処するくらいかな。
ずっと気づかなかったのですが、RがUbuntuの公式リポジトリに入っているんですね。
ということは、最新バージョンにこだわらないのであれば、Rjpwikiに書いてある手順を踏まずともRをインストールすることができます。端末から
sudo apt-get install r-base
sudo apt-get install r-cran*
の2行くらいでいけるみたいです。
UbuntuのバージョンによってRのバージョンも変わるようです。Ubuntu12.04ではR 2.14でした。特に不便はないみたいです。
何事も公式リポジトリ内で済ませられればそれに越したことはないですね。
ということは、最新バージョンにこだわらないのであれば、Rjpwikiに書いてある手順を踏まずともRをインストールすることができます。端末から
sudo apt-get install r-base
sudo apt-get install r-cran*
の2行くらいでいけるみたいです。
UbuntuのバージョンによってRのバージョンも変わるようです。Ubuntu12.04ではR 2.14でした。特に不便はないみたいです。
何事も公式リポジトリ内で済ませられればそれに越したことはないですね。
Calender
| 11 | 2025/12 | 01 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Search in This Blog
Latest Comments
[03/30 川内のばば山田]
[03/30 川内のばば山田]
[08/06 Aterarie]
[07/05 Agazoger]
[07/01 Thomaskina]
Latest Posts
(11/16)
(04/28)
(04/16)
(04/11)
(04/05)
Latest Trackbacks
Category
Access Analysis